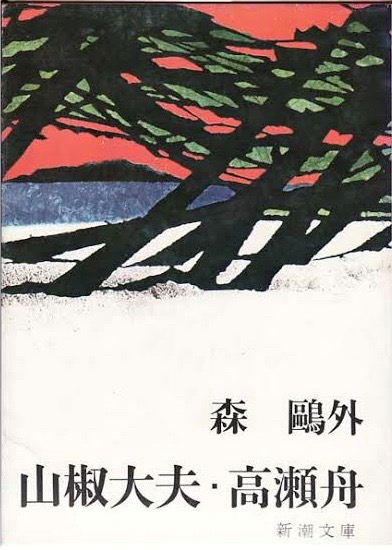森鴎外の高瀬舟
高瀬川の開削と高瀬舟の概要については、歴史探訪のカテゴリーで先日採りあげました。もともと高瀬川が開削されたのは、商業都市として栄えた大坂に集まった木材を、淀川を経由して伏見へ運び、そこで荷揚げして積み替えられて、伏見からこの人工の運河を上って京都の五条付近に運送するという目的でした。さらにこれが京都の中心部にまで延長され、さまざまな物資が大坂から京都市街に運送されるルートとなりました。しかし、時代と共にその目的も多様化していったのか、江戸時代も時代を下ると、京都奉行所で取り調べを受けた罪人がこの高瀬舟に乗せられて高瀬川を下り、大坂奉行所に送られ、そこから佐渡島など島流しのための流人船にのせられて護送されたようです。
森鴎外の『高瀬舟』は、その当時の京都奉行所の役人が書いた随想『翁草』に基づいて書かれました。この小説のテーマは、鴎外自身が自分の小説の解説を書いた『高瀬舟縁起』の中でも“足るを知る事”と“安楽死の是非”とについてであると述べられています。あらすじをまず紹介します。羽田庄兵衛は京都奉行所の役人で、島流しの判決が下った罪人を高瀬舟に乗せて警備、護送する任務を命じられていました。罪人といっても各々には多くの場合事情があり、見送る家族との悲しい別れや罪人自身の嘆き悲しむ姿をいくつも目にし、奉行所役人という安定した職業につきながらも、この高瀬舟での護送を不快な職務として不満に思っていました。また、妻の実家が裕福なことでお金に不自由することもなく、そのような自分の立場に負い目も感じていました。ある日、いつものように高瀬舟で護送にあたった罪人は喜助という貧しい生まれの者でしたが、普段はこれからの島流しの人生を思って悲嘆にくれているはずの罪人の態度とは異なり、いかにも晴れやかな表情をしていました。不審に思った庄兵衛がそのわけを聞くと、「自分はこれまで貧しくてまとまったお金を持ったことがない。それが今回島流しと決まり、牢屋を出る時に、お上から路用金として二百文をいただいた。お金を自分の物にして持っているということは、自分にとっては、これが初めであり、これほどもったいない話はない。」と言って自分の境遇に満足そうにしていました。庄兵衛はそんな彼の姿を、驚きと敬意をもって眺めました。庄兵衛自身はお金や地位を手に入れておりながら、自分にはないものをさらに欲しがっている。それなのに、何も持っていなかった喜助はわずか二百文という路用金で満足し、無意識のうちに『足るを知る』ということが身についている。ここで庄兵衛は自分とこの罪人との間に考え方が全く違っていることを感じました。物語はそのあと嘉助の犯した罪の内容として、病で苦しんでいた弟が自殺におよび死にきれずに苦しんでいるところを見るに見かね、苦しみから解放させるべきか悩んだすえに刺さっていたカミソリを抜き取り、出血多量で死に至らしめたというくだりがあり、これが本当に罪といえるかという鴎外の疑問が投げかけられ、最後は「その是非についてはおかみの判断にゆだねたい」と庄兵衛に言わせて終わっています。この後半のテーマである安楽死に関するインパクトが強いため、前半のテーマである、“足るを知る”というテーマはかすんでしまい、短い小説の中で、不釣り合いに2つの別個のテーマが含まれているのに少し違和感さえ感じます。しかし最近、ブログで「高瀬川を眺めて」という題で高瀬舟をとりあげたのをきっかけに鴎外の『高瀬舟』を読み返していると、実はこの前半の“足るを知る”というテーマが鴎外の大事なメッセージであったように思えました。
この小説は1916年1月号の中央公論に発表されており、くしくもこの号には、吉野作造の民本主義という考え方を提唱する有名な論文が掲載され、まさに大正デモクラシーの民主主義的な風潮(その当時は主権在君であったため国民主権のように民主主義とはいえず民本主義という言葉を作り出した)が盛り上がりをみせていた時でした。ところがこの頃、日本は日清戦争、日露戦争を終え、さらに第1次世界大戦にも参戦していました。さらに、ヨーロッパを主な舞台とした大きな戦争のため、ヨーロッパ諸国は戦争で余裕がなくなり、植民地化していた中国各地の市場からも一旦手を引かざるを得ない状況にあたったため、そのすきに日本は中国に対して対華二十一箇条要求という一方的な要求を出し、その大部分を中国政府に受け入れさせていました。一方、このころまでに鴎外は留学を終え陸軍の軍医でエリートコースにのって出世していました。おそらく戦争で人が負傷、死亡する現実を、一般国民よりも正確に、かつ身近に知っていたでしょう。人道主義の立場からするとどうしてもこの状況はよくない。しかし自分は国から陸軍の軍医という立場を与えられている以上、国の方針に楯ついて反対することもできない。そこが民本主義という言葉で真っ向から論じている吉野作造とは立場がちがいました。そこで、鴎外は、安楽死のような結構インパクトの強いテーマを出して、それを楯にして隠すかのようにしながら、そっと、この“足るを知る”、というテーマをなげかけたのではないでしょうか。鎖国をして自給自足で慎まやかにやっていた近世までの日本はあたかもこの喜助に象徴されるように、富はなくても足るを知っていたのではないか、それが、開国後どんどん富を得ようと富国強兵を進めてきた日本は、この庄兵衛のように、富はある程度持てたのにさらにどんどんないものを欲しがって膨張し、足るを知っていない。このままでいいのだろうか。そして鴎外は、小説の中では、安楽死は難しいからおかみの判断にまかせたいと庄兵衛に言わせていますが、実はこの前半のテーマである”足るを知る”ということについても、本当はおかみに考えてほしいと訴えたかったのではないか。今回、『高瀬舟』を読み返して、日本に向けたそのメッセージを堂々といえなかった鴎外の心の声を聴いたような気がしました。