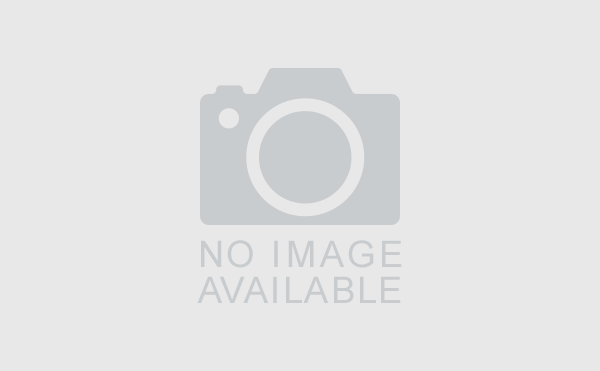高山寺を散策して
神護寺から30分ほど歩くと高山寺の表参道に着きました。神護寺の階段は結構きびしかったので、この調子で歩くのかと思いましたが、10分ぐらいで目的としていた高山寺の国宝石水院に到着しました。
この高山寺は8世紀に創建されており奈良時代に始まる古いお寺です。今の仏教のイメージとは違って、その頃、奈良には華厳宗、倶舎宗、律宗、法相宗、成実宗、三論宗の南都六宗と呼ばれる6つの宗派があり、これらは、仏教の経典を研究する集団でした。今で言えば文系の大学のようなイメージでしょうか。その頃、進んだ知識や学問を身につけている人といえば、仏教経典などを研究しながら、中国の書物を通じて土木建築、天文学、薬学、医術、などいろいろな知識に接している僧侶でした。奈良の中央政府はこれらの人たちを囲い込んでその人たちの知識を独占しようとしていたため、仏教の民間への布教は禁止していました。そして多くの宗派は、戒律を守り、厳しい修行によってはじめて人々が悟りの境地に至れるのだという、選ばれた人たちのみぞ知る仏の道だったのです。その後、平安時代になると、最澄や空海が現れ、貴族が現世で御利益を得たいという風潮と結びつき、神護寺にみられたような密教なども流行して、徐々に南都仏教はすたれていきます。ところが平安時代末期には日本が末法(釈迦が死んで2000年以上たつと世の中がどん底に陥るといった悲観的な時代)に入るという思想が流行し、上層階級である貴族と結びつくだけならまだしも、一般庶民に布教を行い、仏の教えはありがたく、どんな人でも救ってくれますよ、といったことを言い出す僧侶が出てきました。戒律も気にしなくていいよ、ただ南無阿弥陀仏と言ってお祈りしたら極楽に行けるように救ってくれますよ、と。この頃、まだまだ旧仏教の信者が多かったのですが、鎌倉時代になるとこのような鎌倉新仏教と呼ばれる教えは一気に日本各地に広がり始めました。こうなると南都六宗の僧侶たちも反発しだします。南都六宗はこの頃には、法相宗、律宗、華厳宗の3つぐらいしか残っていませんでしたが、「なんだよそれ、戒律を守れよ、厳しい修行もしないでそんな簡単に往生できるかよ」と言って、新仏教を批判しだします。特に、浄土宗系の僧侶は、旧仏教側の圧力をうけて都から遠く、越後、関東、四国などへと追放されることになりました。しかし一方で、旧仏教側も新仏教が重視した民衆救済の方にも目をやり始めながら、奈良時代に建てられて衰退していた寺院の復興を手掛ける人たちもでてきました。
すたれていた高山寺も、鎌倉時代にそのような背景のもとで再興されました。高山寺はもともと華厳宗の寺院でしたが、そこを拠点にして、華厳宗再興の祖とも呼ばれる明恵(別名は高弁)は、老朽化していた高山寺を再興し、浄土宗を始めた法然を厳しく批判するため「摧邪輪」という仏教書を著述しました。石水院には、その明恵の肖像画とされる「明恵上人樹上座禅図」という絵が模写ではありますが展示されています。高山寺は山寺ですので、自然を利用していろいろな所で修行していたのでしょうか、この絵には、木の上に座禅を組んでたたずんでいる明恵上人の姿が描かれています。法然に真っ向から論戦を挑んだという点で、かなり厳しい相貌を予想するところですが、実際にみると、穏やかな、何か悟りの境地に近づいているような表情でちょこんと座禅している姿が描かれていて印象的でした。

https://tomdojomaster.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_6962-225×300.jpg
ところでこのように高山寺は明恵によって再興される前にはおそらくかなりすたれていた寺院だったでしょうし、僧侶も粗末な生活でほそぼそと寺院の運営をやりくりしていたのだろうと想像します。ところが、その中で、平安時代後期、都では院政という政治システムが始まっていた頃に、高山寺には鳥羽僧正覚猷というユニークな僧侶がいました。彼は「鳥獣(人物)戯画」と呼ばれる絵巻物を描いたとされています。この作品は甲乙丙丁4巻からなり、甲巻は擬人化された動物を描き、乙巻は実在・空想上を合わせた動物図譜となっています。丙巻は前半が人間風俗画、後半が動物戯画、丁巻は勝負事を中心に人物を描いています。特に甲巻は、動物たちの遊戯をいきいきと描いていて、さまざまなところでわれわれも目にする機会が多いものではないかと思われます。甲乙巻が平安時代後期の成立、丙丁巻は鎌倉時代の制作と考えられています。擬人化された動物たちが人間のように振る舞う様子、特に僧侶のように振っているのではないかと思われるシーンや賭博遊びのシーンなどが描かれていることから、当時の仏教界や世俗を風刺する目的があったという見方があります。平安時代になって最澄や空海が始めた宗教も、この頃には日本各地に荘園を所有して勢力をもち始めるなど、世俗化してきている面もありました。そのような世間の姿を、高山寺から都を遠くにながめながら風刺したかったのでしょうか。ちなみにこの作品は世界最古の漫画と言われています。展示されていた「鳥獣戯画」をみて、外国人カップルが「アニメみたいだね」と一瞬チラ見して去ろうとしたので、“Do you know this is the oldest animation in the world?”と、言葉をかけると、“Really?”と言って驚き、しばらく見入っておられました。
https://kosanji.com/chojujinbutsugiga/
石水院を出ると、すぐ前には茶畑があります。もともと茶は、平安時代に博多などでは既に伝わっていたようですが(昨年の大河ドラマでも紫式部が博多で飲んでいるシーンが登場しました)、公式に輸入されたのは、禅宗の一宗派である臨済宗を開いた栄西が2度中国の宋に渡り、宋から持ち帰り、茶の効用について1211年「喫茶養生記」という書物に著したのが始まりでした。ちょうどその頃日本では、源実朝が北条氏に政治の権力を奪われて二日酔いの日々でしたが、「二日酔いにも効きますよ」と言って、持ち帰った茶を献じたと言われています。この栄西が持ち帰った茶を高山寺の明恵に与え、明恵が寺の敷地に植えたのがこの茶畑の始まりです。このためこれは日本最古の茶畑と言われています。ここの茶が宇治に伝えられて、それが民衆にも広まることとなります。鎌倉時代に再興されたこのような旧仏教集団にも、新仏教にならい民衆救済に目を向ける動きがみられるとされていますが、明恵は、自らは厳しい修行に励む一方で、戦乱を逃れた女性や子供の救済に尽力するなど、乱世の時代にたくさんの人々を導いたことで知られています。今や茶は日本人の日常生活になくてはならない存在となっており、この茶を広く民衆に広めるもとをつくった明恵の功績は大きいと思いました。

https://tomdojomaster.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_6965-300×225.jpg
ちなみに「茶」という言葉の語源は中国語に由来し、世界中で広東語がルーツの「チャ」と福建省がルーツの「ティー」の2つの系統に分かれて伝播しました。広東語がルーツの「チャ」は陸路を通じてアジアや東欧諸国に伝わり日本語の「茶(チャ)」、朝鮮語やロシア語の「チャイ」になりました。一方、福建省ルーツの「ティー」は海路を通じて西欧、北欧、南アジアに伝わりました。英語のteaはこの系統です。
帰りのバス待ちながら、日陰に腰かけてペットボトルの茶を飲みました。いくら明恵上人でも、800年後に寺の近くでこんな姿で茶を飲んでいる風景は想像できなかったでしょう。