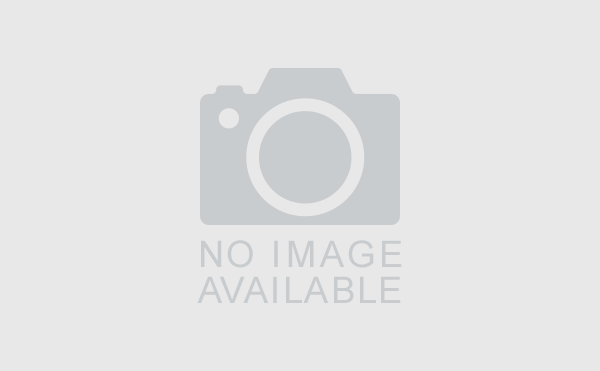縄文展
京都文化博物館で「世界遺産 縄文」と題したテーマの特別展をしていましたので先日、見てきました(図1)。
 図1:縄文展を行っている京都文化博物館
図1:縄文展を行っている京都文化博物館
まず縄文時代に入る前の日本の様子を想像します。それまでは更新世(いわゆる氷河期)の寒い時代が長く続き、日本はアジア大陸と地続きでした。この間に、マンモス、ナウマンゾウ、オオツノジカなど大型生物とともに大陸から一部の人たちが現在の日本の場所にもやってきました。ところが、紀元前1万年前後頃に完新世と呼ばれる時代に入ると地球の温度が上昇し、それまで海の中の氷だったところが解けて海抜がどんどん上昇した結果、海が広がり、日本は大陸と離れ離れになりました。これが縄文時代の始まりで、紀元前3世紀ごろに弥生時代に入るまでの実に7000年以上(説によってはさらに長い間)続いた時代です。気候が変わり、大型動物はいなくなって猪や鹿などすばしっこい小型の動物が増えました。このような生活環境でわれわれの祖先はすばらしい文化を作り上げました。
まず何といっても縄文時代という名前の由来になった縄文土器です。現在では2022年に中国で2万年前の土器片が発見され、これが世界最古とされていますが、最近までは、紀元前1万1000年前(縄文時代草創期)の日本の縄文土器が、世界最古の土器とされていました。しかし世界的にみても最古級の土器が日本で作られていたことは確かです。博物館には、縄文時代中期の火炎土器と呼ばれる炎のデザインをした土器や(図2)、縄文時代晩期の精巧な亀ヶ岡式注口土器(図3)なども展示されていました。この注口土器などは、今の時代でも客人をもてなすのに十分通用するくらいすばらしいできばえです。特にこの時代は東北地方を中心に、人が集まっていたようで、このような縄文文化が東北地方を中心に花開いていました。土器の製作とともに動物の土製像も作られ、この猪の像などは、生き生きとしていてかなり精巧につくられており、これが何千年も前の我々の祖先が作ったものとは驚かされます(図4)。小型のすばしっこい動物を獲得するため、縄文時代には弓矢が使われるようになり、落とし穴なども作っています。また海の幸も積極的にとらえようとして網が張られたり、銛なども使われ、漁労も発達しました。
 図2:縄文中期の火炎土器
図2:縄文中期の火炎土器
 図3:精巧な縄文晩期の亀ヶ岡式注口土器
図3:精巧な縄文晩期の亀ヶ岡式注口土器
 図4:ユニークな猪の土製の像
図4:ユニークな猪の土製の像
そんな何千年も前の大昔に、黒曜石、ヒスイ(硬玉)、サヌカイトなど、限られた場所でしか採れない鉱石が遠く離れた地域でみつかっており、予想以上に人々は遠隔地に行って交易していたこともわかっています。例えば黒曜石は北海道の白滝、十勝、長野県の和田峠、大分県姫島、熊本県阿蘇、伊豆七島の神津島など特定の地域でしか採れず、また一つの黒曜石を見れば、それがどこで採れた黒曜石であるかが鑑定できるそうです。そのため、例えば九州の黒曜石が遠く青森にまで運ばれてきていることが判明したりしています。このような交易には歩いて遠方に行くこともあったとは思いますが、すでにこの頃は、原始的ではあるでしょうが外洋航海術も身につけていたこともわかっています。これを裏付けるように、伊豆神津島の黒曜石が本州で見つかっていますし、もっと驚くべきことには、詳細はよくわかりませんが日本の縄文土器に類似した土器が南米ペルーでも発見されているそうです。
何千年も前に、日本に住み着いた我々の祖先が、遠方の地域に行って、どのような言葉を使って交易をしていたのでしょうか。少なくともこの縄文時代は貧富の違いはなく、人々が平和に助け合って生活していたと考えられています。1つ興味深い展示がありました。それは科学的な解析により、生まれつき身体が不自由で、おそらく生まれて以来、出歩いたりはできず人々に世話してもらっていたのであろうと考えられている人骨でした。この人物は、おそらくその当時の平均寿命と思われる30~40歳ごろまで、周りの人たちに世話してもらいながら生きていたらしいのです。逆に言うと、この頃は、縄文時代以前の土器がなく食料を生のままかあるいは直接焼くかして食べていた時代とはちがって、煮炊きすることができるようになって採集生活の段階ではありますがそれなりにグルメの時代だったようで、食については豊かな生活ができていたのかもしれません。もう一つ興味深かったのは、おそらく人々に飼われていたと思われる犬が埋葬されている遺跡の写真でした。素朴で平和な人間らしい共同生活を営んでいた縄文人の姿を想像しました。